猫が蜘蛛を食べても問題ありませんが、多量に摂取すると寄生虫やクモの骨格が喉に詰まる可能性もあるので注意が必要です。
家庭によく出る一般的な蜘蛛は、大型のアシダカグモ、バツ印の巣を作るのが特徴的な小型コガネグモや、色彩が毒々しいジョロウグモが出ます。
しかし、どれも無毒なので、猫が数匹食べた程度では直ぐに健康被害が出る事はありません。
ただ、殺虫剤で蜘蛛を殺した場合は、殺虫成分を含んだ蜘蛛を猫が食べる事になるので、殺虫剤で駆除した蜘蛛は、猫が食べないように直ぐに処分するように注意しましょう。
記事の要約とポイント
- 猫が蜘蛛を食べる事は基本的には問題ないが、セアカゴケグモ・ハチグモは注意。(殆どいない)
- 猫が食べると危険な蜘蛛は他にもあり、農薬が散布された直後の蜘蛛や、寄生虫のある蜘蛛を食べると健康被害の原因となる。
- 猫についた蜘蛛の巣はタンパク質で毒は無いので、触っても安心だがベタベタして中々取れない事も。
スポンサーリンク
猫が蜘蛛を食べる原因は?食べても大丈夫!?特に問題なし
猫は動くものなら何でも追いかけて捕まえたがり、蜘蛛も例外ではありません。
うちの猫も、よく蜘蛛を見つけては追いかけて遊んでいますが、遊んでいると次第に興奮して大抵は食べてしまいます。
蜘蛛は見た目から毒がありそうで、猫に危険が無いのか心配になりますが、殆どの蜘蛛は無毒なので、食べても心配いりません。
最近の昆虫食ユーチューバーの中では、人が蜘蛛食べている姿すらよく動画で見かけます。
家庭にはよく大型で、手のひらサイズのデカいクモの代表である、アシダカグモや、赤と黒と黄色が毒々しいジョロウグモ、バツ印の蜘蛛の巣が特徴的な小型コガネグモが出ます。
しかし、どれも無毒で毒は無いので安心して大丈夫です。
どこの家庭にも良く出るアシダカグモは猫が食べる代表の蜘蛛!だけど巣を作らない益虫です。
アシダカグモに関する生態は、下記の記事でまとめていますので、興味のある方は是非ご覧ください。

もし、猫が蜘蛛をたべてしまう事について気になるのであれば、猫が居る家庭で気軽に殺虫剤を使うわけにもいきません。
そんな時には、食物由来の天然成分を使った虫除けがお勧めです。
ペットに安全という事は、子供にも安全ですね。
参考までに、猫が蜘蛛を食べる理由についてテーブル形式の表にまとめてみました!参考までにご覧ください。
| 理由 | 説明 |
|---|---|
| 捕食本能 | 猫は本来の捕食者であり、小さな生物を狩る本能があります。 |
| 遊びの一環 | 猫は狩りの動作を遊びとして楽しむことがあり、蜘蛛を追いかけることもあります。 |
| 環境の清掃 | 猫は自分の周囲を清潔に保つために、虫を捕まえて食べることがあります。 |
| 栄養の補給 | 蜘蛛は高タンパク質であり、猫にとって栄養源となることがあります。 |
| 好奇心 | 猫は好奇心が強く、新しいものを探求するために蜘蛛に興味を持つことがあります。 |
猫が蜘蛛を食べる!対策は?
遊ばせる
広い室内
玩具
十分なごはん
おやつ
猫が蜘蛛を食べる時に出来る対策は、ストレスの発散です!広い室内で、自由に遊ばせたり、狭い室内でも飼い主と十分に遊ぶことで猫の首領ホウン脳が満たされます。
ただし、蜘蛛を食べてしまっても目立った健康被害が出る事は少なく、理由は殆どの毒はタンパク質で胃酸で分解されてしまうからです。
- 昆虫を食べてしまう原因・理由は狩猟本能?
- 食べるのを防止する!害虫駆除して猫の誤食防止!
- 危険な蜘蛛の解説!セアカゴケグモ・ハチグモは危険!
- ゴキブリ・アシダカグモを食べた猫の感染症は?
昆虫を食べてしまう原因・理由は狩猟本能?
猫が蜘蛛を食べる理由は、主に狩猟本能・遊び・栄養補給の3つが考えられますが、家ネコの場合は単に遊びでじゃれている事が多いかもしれません。
猫はもともと肉食動物であり、野生の猫は獲物を捕らえて食べる習性があるので、家猫でもその本能が残っており、動くものを見ると追いかけたり、捕まえたりして遊びます。
蜘蛛も動く獲物として猫にとって魅力的な存在であり、じゃれ合うように捕まえて遊んでいるうちに食べてしまうことがあります。
他にも、子猫や若い猫は、特に遊び好きな傾向があり、蜘蛛を捕まえてもすぐに食べるのではなく、長時間じゃれ合ったり、おもちゃのように振り回したりして遊ぶことがあります。
その過程で誤って食べてしまうこともありますが、先ほど解説した通り、家庭に出る殆どの蜘蛛は無毒なので心配いりません。
蜘蛛はタンパク質や脂肪分が豊富に含まれており、猫にとって栄養価の高い獲物なので、野生の猫や栄養不足の猫は、獲物を積極的に捕食して食べることで栄養を補給します。
上記以外にも、誤認やストレスが理由で猫が蜘蛛を食べる場合があります。
子猫の場合、動くもの全てを餌と認識してしまうことがありますので、蜘蛛を昆虫と間違えて食べてしまうことがあります。
猫がストレスを感じている場合、正常な判断ができずに、普段食べないものまで口にしてしまうことがあります。
猫が蜘蛛を食べることは、基本的に問題ありませんが、毒のある蜘蛛・寄生虫のいる蜘蛛・農薬がかった蜘蛛の場合は注意が必要です。
蜘蛛の中には、猫にとって毒を持つ蜘蛛もいるので、猫が蜘蛛を食べた後に、嘔吐、下痢、よだれ、ふらつきなどの症状が現れた場合は、すぐに動物病院を受診する必要があります。
蜘蛛の中には、猫に寄生虫を感染させるものもあり、猫が頻繁に蜘蛛を食べる場合は、寄生虫の駆虫薬を定期的に投与することが大切です。
最も危険なのが、農薬を使用した場所にいる蜘蛛は、農薬が付着している可能性があります。
その為、猫がそのような蜘蛛を食べることで、農薬中毒を起こす可能性があります。(そもそも猫を農薬を散布した危険な場所に近づけないように配慮しましょう)
猫が蜘蛛を食べるのを心配する場合は、猫に与えるフードを栄養バランスのとれた高品質なものにすることで、猫が獲物を捕食する必要性を減らすことができます。
また、家の周りから蜘蛛の巣を取り除いたり、蜘蛛が寄り付きにくい環境を作ったりすることで、猫が蜘蛛を捕まえる機会を減らすこともできます。
殆どの家ネコの場合は、運動不足や暇つぶしに蜘蛛や虫を追いかけている事が多いと思うので、時間を決めて疲れるまでしっかり遊んであげる事も、虫の誤食防止に有効です。
食べるのを防止する!害虫駆除して猫の誤食防止!
人によっては、蜘蛛を見るもの触るのも抵抗がある方もいると思います。
猫に害がない天然成分の虫除けも存在しますが、猫に直接虫除けスプレーを噴射するのはやめた方がよいと思うので、そういう時は下記の商品が便利です。
アース製薬から販売されているのですが、クリップタイプでペットの首輪に取り付けることが出来ます。

特に、大型のアシダカグモは、見た目の狂暴性からとびかかってくるのではないかと思いがちですが、殆どの蜘蛛は自分から向かってくることはありません。
蜘蛛が巣を作らないようにすれば、自然とクモは居なくなりますが、蜘蛛は益虫である事が多いです。
蜘蛛を完全に駆除してしまうと、今度はゴキブリやムカデ等の不快害虫を猫が食べる事になりかねませんので、注意が必要です。
また、蜘蛛の巣はタンパク質で出来ているので、猫が通ったりすると猫の毛に張り付く事があります。
蜘蛛の巣には毒性はありませんし、単にべとつくだけですので、タオルなどで猫の体を拭いてあげれば簡単に落ちる事が多いです。
特にジョロウグモの巣の粘着性は高く、猫につくといつまでもベタベタしています。
蜘蛛の巣除去の効率的な方法に関しては、下記の記事で解説していますので、是非ご覧ください。
ハイターは強アルカリ性の液体なので、猫にかける事は出来ませんが、タンパク質なので、しつこい蜘蛛の巣の汚れはハイターで落とす事は可能です。
蜘蛛は同じ場所に巣を作る習性があるので、猫がいつも同じ場所で蜘蛛の巣に引っかかるようなら、猫の通り道にハッカ油スプレーを撒くのも忌避効果が期待できます。
但し、猫は精油系の強い匂いを嫌いますので、ハッカ油スプレーをした場合は、匂いが消えるまでその場所に猫が立ち入らないよに注意する必要があります。(他の殺虫スプレーも同様です)
危険な蜘蛛の解説!セアカゴケグモ・ハチグモは危険!
日本で猫が食べると危険な蜘蛛は、主にセアカゴケグモとハチグモの2種類です。
セアカゴケグモは、日本全国に分布する毒グモで、体は黒く、腹部には赤い斑点があります。

神経毒を持ち、刺されると激痛や腫れ、吐き気、嘔吐などの症状が現れる事があり、重症の場合は、呼吸困難やけいれん、最悪の場合は死に至ることもあります。
ハチグモは、体長が1~2cmほどの小さな蜘蛛ですが、見た目が蜂にそっくりなのが特徴で、腹部が茶色や黒色で、背中に白い斑点があります。
毒性はセアカゴケグモほど強くはありませんが、刺されると強い痛みや腫れ、発熱などの症状が現れます。
上記以外にも、海外には猫にとって危険な蜘蛛が多数存在しますので、猫が海外旅行中に蜘蛛を食べてしまった場合は、念のため動物病院を受診することをおすすめします。
海外旅行中に猫が蜘蛛を食べたと思われる場合は、以下の点に注意してください。
猫の様子を観察し、嘔吐、下痢、よだれ、ふらつきなどの症状が現れないかを観察し、もしこのような症状が現れたら、すぐに動物病院を受診してください。
可能であれば、猫が食べた蜘蛛の種類を特定すると、動物病院での治療に役立ちます。
猫が蜘蛛を食べることは、基本的に問題ありませんが、上記の危険な蜘蛛や、猫が異変を示している場合は、適切な対処が必要です。
猫に安全な虫よけは、アース製薬のサイトで詳しく解説がありますので、興味のある方はご覧ください。
ゴキブリ・アシダカグモを食べた猫の感染症は?
猫がゴキブリを食べた場合、大丈夫ですか?
猫は自然界で小さい虫を捕まえる能力に優れています。
特にゴキブリは一般的に猫の好物となることがありますが、ゴキブリを食べた際のリスクについて考える必要があります。
ゴキブリにはさまざまな病原菌や寄生虫が含まれている可能性があり、猫がこれらを摂取することで感染症を引き起こすこともあります。
ただし、猫が一度ゴキブリを食べたからといって、必ずしも感染症になるわけではありません。
多くの猫は強い免疫を持っており、少量のゴキブリを食べても問題ないことが多いです。
とはいえ、猫の健康状態や環境によってリスクが異なるため、注意が必要です。
また、ゴキブリが持つ病原体によっては、猫に対して深刻な影響を与えることもあります。
特に、寄生虫感染や消化器系の問題を引き起こすことがあるため、猫がゴキブリを食べた場合は、観察を怠らないことが重要です。
アシダカグモを食べた猫は大丈夫ですか?
アシダカグモは、その大きさと特徴的な姿から、猫が興味を持つことがあります。
猫がアシダカグモを食べることはありますが、この場合も感染症のリスクが考えられます。
アシダカグモは一般的に毒を持たないため、猫が食べても直接的な危険は少ないとされていますが、注意が必要です。
アシダカグモを食べた場合、猫がアレルギー反応を示すこともあります。
特に、初めて食べる場合や体調が優れないときは、アレルギー反応のリスクが高まります。
もし猫がアシダカグモを食べた後に異常を示した場合は、すぐに獣医師に相談してください。
猫が蜘蛛を食べた場合、どんな症状が出ますか?
猫が蜘蛛を食べた場合、特に以下のような症状が見られることがあります。
- 嘔吐
- 下痢
- 食欲不振
- lethargy(無気力)
これらの症状は、猫が食べた蜘蛛に依存します。
特に毒を持つ蜘蛛を食べた場合、より深刻な症状が現れる可能性があります。
猫が蜘蛛を食べた後に上記の症状が見られた場合は、早急に獣医師に相談することが重要です。
猫が虫を食べる理由は何ですか?
猫が虫を食べる理由にはいくつかの要因があり、猫は本能的にハンターであり、小さい虫を捕まえることが好きです。
虫を捕まえることで、狩猟本能を満たすことができ、猫は食事の一部として虫を摂取することもあります。
特に、自然の中で生活している猫は、虫を食べることが一般的で、猫の食事には特定の栄養素が含まれている場合があります。
虫は高タンパク質であり、猫にとって良い栄養源となることがあります。
したがって、猫が虫を食べるのは自然な行動なのです。
猫が食べた場合の対策は?
猫がゴキブリやアシダカグモを食べた場合の対策として、まずは観察が重要で、猫が異常な行動や症状を示した場合は、すぐに獣医師に相談することが必要です。
また、普段から猫が虫を捕まえないように、家の中を清潔に保つことも大切です。
さらに、猫が食べた虫の種類を特定することができれば、より具体的な対策を講じることができます。
例えば、特定の虫が多い場合、その虫の駆除を行うことで、猫の健康を守ることができます。
猫の健康を守るためには、日常的なケアと観察が欠かせません。
以上のように、猫がゴキブリやアシダカグモを食べた場合のリスクや対策について理解を深めることが大切です。
猫の健康を守るために、これらの情報を参考にしてください。
猫が蜘蛛や昆虫を食べるのを防止できるおもちゃは?
猫は本来、優れたハンターの本能を持ち、小さな蜘蛛やゴキブリを見つけると夢中で追いかけ、時には「食べる」行動に出ます。
しかし、猫が蜘蛛や虫を食べてしまうことは健康リスクを伴い、寄生虫の感染など危険性が指摘されています。
以降では、猫が蜘蛛を食べる行動を防ぐための安全なおもちゃの選び方と、猫の狩猟本能を正しく満たすための工夫を詳しく解説します。
特に、電子駆動型や羽根付きのアイテム、さらに噛んだり捕まえたりできるおもちゃなど、猫が小さい虫を捕まえる感覚を楽しみながら、室内で安全に遊べるものを厳選しました。
猫が虫食べる衝動を抑えられる環境づくりも重要です。
清掃を徹底して蜘蛛の出現を防ぐ方法や、猫が部屋の隅でゴキブリや蜘蛛に興味を示さないようにする工夫。
また高品質なキャットプレイグラウンドの設置など、猫が快適に暮らせる空間の整え方についても触れています。
猫が安全に遊び、健康を保ちながらハンティング欲求を満たせる環境を作るためのヒントをご紹介します。

猫が蜘蛛を食べるのをやめさせたい場合の対策
電子駆動型
キャットタワー
トンネル
ボール
フェザー
猫が蜘蛛を食べてしまうのは、狩猟本能からこのような行為に出る事が多く、遊びに満足していない場合やストレスを感じている場合があります。
飼い主は、猫のストレスや運動不足を考慮して、毎日遊び、運動させることが必要です。
- 猫が蜘蛛を食べるのを防ぐ!おすすめの安全おもちゃ5選
- 猫の狩猟本能を満たす!蜘蛛以外をターゲットにするおもちゃの選び方
- 室内でも安全!猫が蜘蛛を食べないようにする工夫とアイテム紹介
- なぜ猫は小さい虫を捕まえるのが好きなのか知恵袋を解説
猫が蜘蛛を食べるのを防ぐ!おすすめの安全おもちゃ5選
猫は本来、優れたハンターとしての本能を持っており、小さな虫や蜘蛛を見ると反射的に「捕まえたい」「食べたい」という衝動が湧き上がります。
蜘蛛を食べてしまうことは、猫の健康に悪影響を与える可能性もありますが、猫がこの本能を抑えるのは簡単ではありません。
そこで今回は、猫が蜘蛛を食べるのを防ぐために役立つ、安全かつ楽しいおもちゃを5つご紹介します。

電子駆動型おもちゃ
電子駆動型おもちゃは猫の興味を引くために特に効果的なおもちゃです。
自動で動くため、猫が「捕まえたい」という衝動を満たすことができ、蜘蛛や他の小さい虫に対する興味を分散させることができます。
おもちゃが不規則な動きをすることで、猫はさらに興奮し、夢中になって遊ぶことができます。
たとえば、動きの早いゴキブリ型のおもちゃや、虫を模した羽根付きの電子おもちゃなどがあります。
こうしたおもちゃは、安全かつ長時間遊ばせることができるため、猫が部屋で蜘蛛や蛾などを見かけても、そちらに注意を向けないようにする助けとなります。
キャットタワーとハンティングおもちゃの組み合わせ
猫が室内で活発に遊ぶためのキャットタワーと、ぶら下がるおもちゃの組み合わせも効果的です。
キャットタワーは猫の運動欲求を満たし、ハンティングのシミュレーションができる場として非常に役立ちます。
蜘蛛や小さな虫を捕まえようとする猫の本能を代替できるため、特に「なぜ猫が虫を食べるのか?」という疑問に対する一つの答えとしても有効です。
カラフルなボールやフェザーおもちゃ
カラフルで軽いボールや羽根付きのおもちゃは、猫が自ら追いかけたくなる自然な動きや色を持っています。
とくに羽根付きのおもちゃは、蜘蛛やゴキブリの動きを連想させるため、猫は夢中になって遊ぶ傾向があります。
こうしたおもちゃは定期的に変えることで飽きが来にくく、猫の狩猟本能を適度に満たしてくれます。
特に、猫が「虫食べる」行動をしなくてもいいように、これらのおもちゃで日々満足させておくことが重要です。
スクラッチボードと隠れんぼタイプのおもちゃ
スクラッチボードにトンネルや隠れんぼタイプのおもちゃを取り付けると、猫は「隠れたものを探す」という遊びを楽しむことができます。
猫が蜘蛛やゴキブリを捕まえようとする場面を避けるためにも、こうしたおもちゃでしっかりとした遊びの代替手段を提供することが効果的です。
猫が隠れた小さなものに反応することで、日常の中で「虫を食べる」衝動を少しでも抑えることが可能です。
追跡型レーザーポインター
レーザーポインターは猫がすばやく動くものに反応する傾向を活かし、蜘蛛や虫に向かう前に遊びのターゲットを切り替えることができます。
ただし、レーザー光そのものは猫にとって無形のものなので、追いかけるだけでなく、最終的に捕まえられるおもちゃと組み合わせて遊ばせるとより効果的です。
猫が蜘蛛を食べてしまうのは本能なので、本能を満たすために猫がおもいっきり遊べる大型猫用のホイールがお勧めです。
猫をちょっとトレッドミルで遊んでやれば、スタミナの無い猫は直ぐに疲れるので、蜘蛛を食べる気力もなくなるでしょう!
猫の狩猟本能を満たす!蜘蛛以外をターゲットにするおもちゃの選び方
猫の狩猟本能は、動くものに対して自然と反応する性質があるため、小さな虫や蜘蛛を見つけるとすぐに捕まえようとします。
これを抑えるためには、猫が「捕まえる」感覚を満足させられるおもちゃを提供することが大切です。
以下に、蜘蛛以外をターゲットにするのに役立つおもちゃの選び方をご紹介します。

動きのあるおもちゃを選ぶ
動きのあるおもちゃは、猫の興味を引きやすく、狩猟本能を刺激します。
たとえば、フェザー付きのロッドや不規則に動くボール、電子で動く「おもちゃネズミ」などが挙げられます。
これらのアイテムは、ゴキブリや蛾など、猫が日常的に見かける「小さい虫」に似た動きをするため、猫が夢中になって追いかけます。
こうして猫のハンティング欲求を満たすことで、蜘蛛などを実際に食べる行動を減らすことが期待できます。
多種多様な素材のおもちゃを試す
猫のおもちゃには、布、ゴム、フェザー、シリコンなど、さまざまな素材があります。
蜘蛛を避けつつ猫を満足させるためには、これらの素材を使い分けることが効果的です。
たとえば、羽根の付いたおもちゃは自然界の小さな生物に似ており、猫が反応しやすい一方で、シリコン製の弾むボールなども猫にとって魅力的です。
猫が「捕まえたい」という衝動を自然に満たせるため、蜘蛛以外のターゲットに向けた行動を促進できます。
捕まえやすいおもちゃ
猫は「捕まえた」という感覚を得ることで、満足感を感じます。
特に、蜘蛛や小さな虫の動きに敏感に反応する猫には、捕まえやすいおもちゃが有効です。
蜘蛛に似たサイズである小さなぬいぐるみや、猫が簡単に捕らえられる羽根付きおもちゃなどが効果的です。
さらに、捕まえたおもちゃを咥えたり、引っ掻いたりすることで、狩猟本能を満足させることができ、蜘蛛などに注意が向きにくくなります。
「狩り」をシミュレートできるインタラクティブおもちゃ
インタラクティブなおもちゃは、飼い主が操作して動かすことで猫が「狩り」をシミュレートできるので、蜘蛛を食べる行動を防ぐのに役立ちます。
飼い主と一緒に遊べるおもちゃは、猫にとって非常に楽しい体験となり、また運動不足の解消にもつながります。
これにより、猫が室内で見つけた虫や蜘蛛に向けてしまう関心を減らすことができます。
噛んだり引っ張ったりできる丈夫なおもちゃ
丈夫な素材のおもちゃは、猫が噛んだり、引っ張ったりできるため、蜘蛛を捕まえて食べる行動の代替品として最適です。
猫がしっかりと噛みつけるおもちゃを提供することで、虫を食べる衝動をおもちゃで解消でき、寄生虫や病気のリスクを低減することができます。
特に、小さいサイズのおもちゃで猫が「獲物」と感じることができるものは、狩猟本能を満たし、蜘蛛に対する興味を抑える効果が期待できます。
円形サークル内にボールが転がるインタラクティブな猫のおもちゃは、猫のおもちゃとしてメジャーですね。
転がるボールが猫の好奇心を刺激して、好きな猫はかなりずっと遊んでいます。
室内でも安全!猫が蜘蛛を食べないようにする工夫とアイテム紹介
室内で猫が蜘蛛を見つけ、食べてしまうのを防ぐためには、猫が安全に遊べる環境を整えることが必要です。
ここでは、猫が室内で安全に過ごし、蜘蛛や他の虫を食べないための工夫と役立つアイテムを紹介します。

羽のついた猫用タンプラーは、猫の本能をかなり刺激するのでお勧めです!転がっても立ち上がるようにできているので、猫の興味を引く事間違いなしです。
清掃を徹底して蜘蛛の出現を防ぐ
まず、猫が蜘蛛やゴキブリなどの小さな虫に接触しないよう、室内の清掃を徹底することが重要です。
特に、家具の隙間や窓付近は虫が入り込みやすい場所なので、掃除機や除湿剤などを使って環境を清潔に保ちましょう。
また、虫が好む湿気の多い場所には防虫剤を置くなどの工夫をすることで、猫が虫に興味を持つ機会を減らせます。
高品質なペット用カバーと虫よけシートを活用
部屋の隅や家具の下に隠れている蜘蛛に対して、猫が気づきにくくするために、虫よけシートや防虫カバーを使用するのも有効です。
これにより、猫が興味を引くような小さな虫の存在を減らすことができ、同時に家全体の清潔さを保てます。
また、猫が近寄らないような場所を特定し、そこに防虫アイテムを配置することで、猫と虫の接触を防ぐ環境を作り上げることが可能です。
猫が見えない場所に蜘蛛が隠れることを防ぐインテリア配置
蜘蛛は家具の隙間や暗い場所に隠れがちです。
そのため、家具を定期的に移動させ、蜘蛛が隠れやすい環境を減らすことで、猫が蜘蛛を見つけてしまうリスクを低減できます。
猫が遊びやすく、同時に見渡しの良い空間を整え、蜘蛛が猫の視界に入りにくくするインテリア配置を心がけましょう。
窓やドアの密閉を強化する
蜘蛛や小さな虫が屋内に侵入しないように、窓やドアの密閉を強化することも大切です。
窓枠の隙間をコーキング剤などでしっかりとふさぎ、網戸には防虫スプレーをかけることで、虫が入ってくるのを防ぐことができます。
猫が日常的に蜘蛛に触れる機会が減るだけでなく、健康リスクも軽減されるため、定期的に窓やドアのチェックを行いましょう。
キャットプレイグラウンドの活用
猫が夢中になって遊べるキャットプレイグラウンドやキャットウォークを設置することで、猫が部屋全体を監視して蜘蛛を探しに行く行動を抑えられます。
キャットタワーや隠れ家付きのおもちゃが組み込まれたプレイグラウンドは、猫が安全に遊べる環境を提供する事が重要です。
狩猟本能を満たしつつも蜘蛛などの虫に興味を引かれないようにするのに役立ちます。
なぜ猫は小さい虫を捕まえるのが好きなのか知恵袋を解説
猫が小さい虫を捕まえることは、彼らの本能的な行動の一部であり、私たちがこの現象を理解するためには、猫の生態や行動について深く掘り下げる必要があります。
まず、猫は肉食性の動物であり、狩猟本能が非常に強い生き物です。
この本能は、野生で生活していた頃から受け継がれており、小さい虫を捕まえることはその一環です。
猫にとって、小さい虫、例えばゴキブリやアシダカグモなどは、動きが速くて予測が難しいため、捕まえるのが楽しい対象となります。
そのため、猫が虫を見つけると、すぐに興味を持ち、追いかけて捕まえる行動に出るのです。
この行動は、遊びの一環としても捉えられ、猫がストレスを解消したり、運動不足を解消する手段としても機能します。
また、捕まえた虫を食べることで、猫は栄養を摂取することができ、特に高タンパク質な虫は猫にとって良い栄養源となります。
具体的には、虫には猫に必要なアミノ酸やビタミンが含まれており、これが猫が虫を食べる理由の一部と言えるでしょう。
さらに、猫は好奇心が強い動物であり、新しいものに対して興味を示します。
小さい虫は動きが素早く、猫にとっては刺激的な対象となります。
知恵袋などで「猫が虫を捕まえるのはなぜ?」という質問が多く寄せられる理由も、猫の好奇心や遊び心に起因しています。
猫は遊びの中で、捕まえた虫を「獲物」として扱い、その過程を楽しむのです。
しかし、注意が必要なのは、猫が虫を食べた場合に健康に影響を及ぼす可能性がある点です。
例えば、ゴキブリやアシダカグモを食べた場合、虫が持つ病原菌や寄生虫に感染するリスクが存在します。
特に、下痢や嘔吐といった消化器系の問題を引き起こすことがあるため、飼い主は猫の行動を観察し、異常があればすぐに獣医師に相談することが大切です。
また、猫が蜘蛛の巣に引っかかることもありますが、これも猫にとっては遊びの一環として楽しむことが多いです。
ただし、蜘蛛の種類によっては毒を持っている場合があるため、注意が必要です。
猫が虫を食べることには、さまざまな理由があり、その行動は本能や好奇心、遊び心が組み合わさった結果と言えます。
このように、猫が小さい虫を捕まえる理由と、その行動の背景を理解することで、より良い飼い方や健康管理につなげることができるでしょう。
猫の健康を保つためには、日常的な観察と適切なケアが欠かせません。
猫が虫を捕まえた場合の対策や注意点を知っておくことで、愛猫の健康を守る手助けになるでしょう。
以上のように、猫が小さい虫を捕まえる理由は多岐にわたりますが、これを理解することで、飼い主としての役割を果たすことができるのです。
猫が蜘蛛を食べる!原因と対策まとめ
猫が食べても平気な蜘蛛と、食べると危険な蜘蛛が居る事を解説したので纏めます。
猫が食べても問題ない蜘蛛は、家庭によく出る蜘蛛の代表のジョロウグモ、アシダカグモ、小型コガネグモです。

ジョロウグモは、かなり大型の蜘蛛で、大きい毒々しい色の蜘蛛は主にメスのジョロウグモです。
ジョロウグモに毒はありません。
正確には獲物を捕らえる程度の毒は持っているようですが、人には無害と言われています。
また、小型コガネグモも無毒で、巣は特徴的なXの形をしており、ジョロウグモと同様に、巣はタンパク質で出来ており、獲物を捕らえる為にとてもネバネバしています。
タンパク質はハイターで落とせる事も解説しました。
アシダカグモは家に出る蜘蛛で最も大型の蜘蛛で、成長したアシダカグモは手のひらサイズにまで成長する事も珍しくありません。
しかし、巣を作る事はなく、ネズミまでも捕食すると言われる益虫ですので、なるべく殺さないよにしましょう。
猫が食べると危険な蜘蛛は、殆ど見かける事はありませんが、セアカゴケグモやハチグモは毒があるので注意が必要です。
他にも猫が食べると危険な蜘蛛が、農薬や殺虫剤散布直後で死にかけた蜘蛛は、殺虫剤や農薬が含まれているので、猫が食べると健康被害を起こす可能性があります。
寄生虫が居る蜘蛛は猫に感染して体調不良を起こす可能性がありますので、注意が必要です。
家ネコの場合は、大抵の場合が暇つぶしや遊び目的で蜘蛛を追いかけている事が多いので、なるべく猫が蜘蛛や虫を食べるのを防止するなら、時間を決めて猫としっかり遊んであげる事をおすすめします。
参考
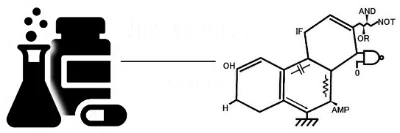










コメント