イヤホンの線が切れた時、どうしていますか?イヤホンを愛用しているあなたにとって、急に音が聞こえなくなる瞬間ほどショックなことはありません。
有線イヤホンの線が切れた時、その不便さを痛感することでしょう!中の線が見えてる状態や、片方の音だけがプツプツと聞こえない時、その原因は断線にあります。
そんな時に役立つのが、簡単な直し方で、自分で修理できるということを知っていると、無駄な出費を抑えられますし、愛着も深まります。
実際、ハンダなしでできる修理方法もありますので、特別な道具がなくても大丈夫です!セロハンテープを使ったり、他のアイテムを駆使して、あっという間に元通りに直すことが可能です。
知恵袋などの情報を参考にしながら、あなたもぜひ自分のイヤホンを救ってあげてください。
断線防止のための工夫や、日常的なケアも紹介しますので、これを機にイヤホンの扱い方を見直す良いチャンスです。
イヤホンの線が切れるのは危ないことですが、正しい知識と簡単な方法で、長く愛用することができ、使い方や保管方法を見直し、イヤホンを大切にしましょう。
記事の要約とポイント
- イヤホンの線が切れるのを防ぐためには、取り扱いに注意が必要です。特に、使わない時はセロハンテープで巻いて保管するなど、簡単な方法で摩耗を減らしましょう。
- もしイヤホンの線が切れた場合でも、ハンダなしで修理する方法があります。中の線が見えてる時は、しっかりとつなぎ直し、セロハンテープで固定するだけで、再度使える状態に戻ります。
- 片方のイヤホンから音が聞こえない場合、断線が疑われます。プツプツ音がすることもあるので、まずは線の状態を確認し、修理を行うことが大切です。
- イヤホンの修理方法や断線防止策について、知恵袋などの情報を参考にすることで、他のユーザーの経験を活かし、より効果的な対策を取ることができます。
スポンサーリンク
イヤホンの線が切れた!修理する前に知っておくべきこと
有線イヤホンの線が切れたら、音がブツブツ切れる事や急に聞こえなくなる事はよくある事ですし、両耳のイヤホンが断線しなくても、片耳だけ聞こえない事も有線イヤホンだとよく起こります。
イヤホンの線画切れるのは、無理な力を加えて銅線が内部でねじ切れたり、ハンダが内部で外れて接触不良を起こしている事が殆どです。
イヤホンの線画切れても、AC電源に繋いでいるようなオーディオ機器で無ければ感電する心配は全くありません。
今回の記事では有線イヤホンの線が切れたり、線の中が見えている状態や聞こえなくなった時の簡単な直し方と、断線防止!
ハンダなしで修理は可能か?どんな道具や材料が必要?イヤホンが断線すると感電して危ないって聞くけど?こんな悩みに技術的な解説を交えてお答えします。
イヤホン線が切れたりすると、感電して危ないというのは誤情報!そもそもイヤホンを駆動するには人が感電する程の高電圧・電流が必要ないからです。
イヤホンを駆動するのに必要な電圧は僅か数mV-1V程度。
線が断線したイヤホンを修理するのにハンダが無くても修理は可能です!但し、スリーブを使用するのでカシメ工具が必要。
イヤホンが片耳しか聞こえないのは四本のうちの線の一本・もしくは二本が断線しているから。(後ほど詳しく解説)
イヤホンの線が切れた時の対処法
イヤホン
線
切れた
修理
簡単
イヤホンの線が切れた場合、修理の前に知っておくべきことがあります。特に、切れた部分が中の線が見えてるとつないでいるデバイスが落下する危険があります。簡単な直し方を学び、ハンダなしで直す方法や、セロハンテープを使った修理方法を参考にしましょう。これで、片方が聞こえない時も自力で対応できます。
- 有線イヤホンの線はなぜ断線しやすいのか?
- 中の線が見えている時の危険性と注意点
- 急に片方だけ聞こえない!その原因と対策
- イヤホン線が切れた!断線すると感電して危ないってホント!?
- 2025年断線に強い!おすすめの有線イヤホンはコレだ!
- Bluetoothの無線イヤホンは簡単に直すのが不可能!メーカー修理へ
有線イヤホンの線はなぜ断線しやすいのか?
イヤホンが断線しやすい場所について、まとめてみました。
| 断線しやすい箇所 | 理由 |
|---|---|
| プラグ部分 | 接続部分で頻繁に曲げられるため、摩耗や断線が起こりやすい。 |
| ケーブルの根元 | ケーブルが曲がったり引っ張られたりすることで、根元部分がストレスを受けやすく、断線が発生する。 |
| イヤフォン本体 | 耳に直接入る部分で、使用中の動きや引っ張りにより内側の線が切れることがある。 |
| ケーブルの中間部 | ケーブルが引っかかったり、物に挟まれることで、物理的な圧力がかかり、断線が生じることが多い。 |
| ストレート部分 | ケーブルが長いため、絡まったり、ねじれたりすることで、内側の線が傷む可能性が高い。 |
これらの場所は、使用中に負荷がかかりやすく、断線しやすい箇所です。
プラグの付け根は、イヤホンを抜き差しする際に負荷がかかりやすく、断線しやすい場所で、プラグの付け根が曲がったり折れたりすることも断線につながります。
ミニジャック部分は、スマートフォンやパソコンなどの機器に接続する際に負荷がかかりやすく、断線しやすい場所です。
また、ミニジャック部分がポケットやバッグの中で擦れたり引っかかったりすることも断線につながります。
コードの分岐部分は、コードが二股に分かれる部分で、この部分はコードが細くなっているため、負荷がかかりやすく断線しやすい場所です。
イヤホンの断線を防ぐためには、以下の点に注意しましょう。
プラグの付け根を無理に引っ張ったり、曲げたりしない。また、ミニジャック部分を丁寧に扱い、擦れたり引っかかったりしないようにする。コードをきつく巻きつけたり、無理に引っ張ったりせず、イヤホンを使わないときは、専用のケースに入れて持ち運ぶ。
また、断線しにくいイヤホンを選ぶことも大切です。断線しにくいイヤホンには、以下のような特徴があります。
- コードが太い
- プラグやミニジャック部分が丈夫
- コードの分岐部分に保護キャップが付いている
イヤホンを長持ちさせるためには、上記の点に注意して使用しましょう。
他にも良くあるのが、イヤホンを洋服に入れたまま洗濯してしまった!という事もあるかと思います。
イヤホンを洗濯すると、内部に電池の無い有線イヤホンは故障する可能性が低いですが、代わりに水が入って乾くまで音割れ等の症状が出る可能性があります。
水が内部に入り込んだ事で、内部がさび付く可能性もあります。
錆びに関しては、特に圧電スピーカーで音を鳴らしているイヤホンに置きやすい故障です。
水は不純物を含み、導体なので、乾かないままで使用すると内部でショートして完全に故障する可能性もあるので、イヤホンを洗濯してしまった場合、乾くまで使用しないよに注意しましょう。
以下の記事は、パソコンのキーボードや、本体、モニターに水をこぼしてしまった時の対処方法ですが、この方法はイヤホンにも応用できるので、併せてご覧ください。
中の線が見えている時の危険性と注意点
結論から言って、イヤホンの線が切れて中の線が見えている場合でも、危険性は特にありません!断線してショートしてもスパークが起きる心配のない低電圧だからです。
注意点をあえて言うなら、断線したイヤホンが原因で、スマホやオーディオ本体を落とさないように注意する事くらいでしょうか。
中の線が見えても、焦げたり、感電したりする危険性はほぼゼロでしょう。
そこで、有線のイヤホンがブツブツ切れて、両耳もしくは片耳だけ聞こえない症状の断線修理について解説します。

断線を修理する方法として大きく分けて二つの修理方法が存在します。
一つ目がハンダを使わずに、スリーブを断線個所に通してカシメ工具でかしめて断線部分を圧着する断線修理方法です。
この断線修理方法の良い所は、ハンダ付けよりも断線修理が簡単で早く終わる点です。
修理には、金属スリーブを使用して工具で圧着するので、どうしても圧着部分がコブになってそこが洋服やカバンに引っかかって取り出しにくくなる可能性があります。
その為、ひっかかりが原因でイヤホン線の断線の原因になる事もあります。
筆者は次に書くハンダ付け断線修理をお勧めします。
ハンダ付けでの断線修理は断線個所をハンダ付けして熱収縮チューブで覆いますので、先のようなコブが出来ずに使用できます。
また、ハンダごてとハンダがあれば、イヤホンジャックの根本部分の断線にも対応できるからです。
イヤホンジャックの根本部分がぐらぐらしてしまうとイヤホンの端子をカットして新たなイヤホンジャックをハンダ付けするしかありません。
他にセロハンテープで張り付けるという方法もお勧めですが、抜本的な解決策とは言えません。
急に片方だけ聞こえない!その原因と対策
有線イヤホンを使用していると、急に片方だけ聞こえなくなることがあります。
この現象は非常にストレスを感じさせるもので、音楽やポッドキャストを楽しむ際には致命的です!では、なぜこのようなことが起こるのか、その原因と対策について詳しく見ていきましょう。
まず、片方のイヤホンから音が聞こえない主な原因は「断線」です。
イヤホンの線が切れた場合、音が途切れることがあり、長期間使用しているイヤホンでは、線の内部が摩耗したり、外的な圧力が加わったりして切れることが多いです。
具体的には、イヤホンのプラグ部分や接続部が特に弱点となり、ここが切れると音がまったく聞こえなくなることがあります。
また、配線が傷んでいる場合も、片方のイヤホンが聞こえない原因となります。
中の線が見えている状態や、外部からの圧力で線がねじれていると、接触不良を引き起こす可能性があります。
このような場合、プツプツとした音が聞こえたり、一時的に音が途切れたりすることが多いです。
ブツブツ状況に陥った場合、まずはイヤホンの状態を確認することが重要です。
耳に入れる部分から線をたどり、どこに問題があるのかを特定します。
注意すべきは、線が切れていたり、断線が起こっている部分で、線が切れていることが確認できたら、修理が必要です。
この際、ハンダなしで簡単に直す方法もありますので、別のセクションでその方法をご紹介します。
対策としては、まずは新しいイヤホンを購入することも一つの手ですが、修理することでコストを抑えることができます。
知恵袋などの情報を参考にしながら、自分で直してみるのも良いでしょう。
セロハンテープを使用した修理方法は、手軽で効果的ですが、抜本的な解決策ではありません。
線が切れた場所をしっかりとつなぎ合わせ、テープで固定することで、再び音を聞くことが可能になります。
このように、片方だけ聞こえないという問題は、イヤホンの断線が主な原因です。
イヤホン線が切れた!断線すると感電して危ないってホント!?
冒頭のポイントでお伝えしたとおり、結論から言ってイヤホンで感電する心配や危険性はありません。
但し、家庭用のスピーカーアンプから取れる有線イヤホンやBluetoothの無線イヤホンでは危険が異なります。

イヤホンの動作電圧は数mV-1V程度の電圧で動作します。
殆どのイヤホンは乾電池式のポータブルなものですので、内部回路的にも大きな電圧を発生させる回路がないので、感電の心配はありません。
ただ、一点注意が必要なのがアンプ付きの家電のスピーカーで、100Vを使用しています。
これが何らかの原因で内部回路がショートしてイヤホン迄漏電していないとは限りません!こういった製品は予測不能なので、テスターや検電器を使用して実際に漏電しているか確認するしかありません。
一例として、安心の日本製HIOKI(日置電機) の検電器の商品リンクを載せておきますね!
イヤホンは、モノにもよりますが安価なものだと圧電スピーカーで簡易的な方法で音を鳴らし、高級なイヤフォンだとコイル方式で音を鳴らして居ます。
圧電スピーカーは低電力で動作しますが、コイルと磁石のイヤフォンだと音質が良い代わりに大きな電力を使用します。
イヤホンの種類や技術的な仕組みについては、下記の記事で詳しく解説していますので併せてご覧ください。
2025年断線に強い!おすすめの有線イヤホンはコレだ!
断線に強いおすすめの有線イヤホンはいくつかありますが、いくつか例を挙げます。
1万円以下
- 高音質と遮音性を兼ね備えたイヤホンです。
- ケーブルは着脱式で、断線した場合でも交換可能です。
- イヤーピースは豊富なサイズが付属しているので、自分に合ったフィット感を得られます。
1万円~2万円
- クリアな音質と自然な音場感を実現したイヤホンです。
- ケーブルはリケーブル対応なので、音質のアップグレードも可能です。
- MMCX端子を採用しているので、ケーブルの選択肢が広いです。
2万円以上
- 重低音域の表現力に優れたイヤホンです。
- ハイレゾ音源にも対応しているので、高音質な音楽を楽しめます。
- 独自の「ハイブリッドドライバーユニット」を搭載することで、クリアな音質を実現しています。
その他
- コストパフォーマンスに優れたイヤホンです。
- 1万円以下で購入できるにもかかわらず、高音質なサウンドを実現しています。
- ケーブルは着脱式で、断線した場合でも交換可能です。
上記はあくまで一例です。自分に合った音質や価格帯、装着感などを考慮して選ぶことをおすすめします。
イヤホンを選ぶ際には、実際に試聴してみることをおすすめします。家電量販店やオーディオ専門店などで試聴できるので、自分に合った音質を見つけてください。
Bluetoothの無線イヤホンは簡単に直すのが不可能!メーカー修理へ
下記の画像は、私が普段使用しているBluetoothの無線イヤホンですが、これが故障した場合は様々な原因が考えられるので、個人的な修復は極めて困難です。
内部は電子回路で部品も小さく、分解する時のネジも無いので、素人が修理するのは不可能に近い為、メーカー修理依頼するのが最も適切な判断です。

イヤホンは、動作電圧が数mVから1V程度なので感電の危険は無いとお話ししましたが、無線のBluetoothイヤホンに関しては別の危険も存在するかもしれません。
画像と同じで筆者が使用しているKenwood KH-BIZ70T-BAは、少々高価ですが音質も良く非常におすすめの日本製イヤホンです。
最近のBluetooth無線イヤホンには、大抵内部にリチウム電池が使われています。
別の記事でも詳細を記述していますが、リチウムは非常に不安定な金属で、空気や水に触れると発火の危険もあるイオン化傾向の高い金属です。
発火するまでの事態になる事はほぼないと思いますが、イヤホンをぶつけたり落としたりして内部のリチウム電池にヒビが入ったまま使用した場合、発火するリスクもあります。
ぶつけたり落としたりしなくても、リチウムは保護回路が故障して過充電・過放電するとそれだけで発火の危険性もあるという事も忘れないでください。
ただ、先ほども説明した通り、発火するような事態に発生する事は稀です。
電池の電圧が低く、電池容量もそれほど大容量のものを必要としない為、もしリチウムがむき出しになる故障に発展しても精々赤熱するか、煙が出る位で終わる事が殆どだと思います。
イヤホンの線が切れたときの簡単な直し方
イヤホンの線が切れたとき、修理する方法を知っていると非常に便利です。
特に、お金をかけずに自分で直せる方法があれば、急な出費を抑えることができる為、ここでは、イヤホンの線が切れた場合の簡単な直し方について詳しく説明します。
まず、修理を始める前に必要な道具を準備しましょう。
必要なものは、ハサミ、セロハンテープ、そして場合によっては接着剤です!これらの道具を用意しておくことで、修理作業がスムーズに進みます。
次に、切れた部分を見つけます。
イヤホンの線を優しく引っ張りながら、どこが切れているのかを確認します。切れた部分が見つかったら、周囲の絶縁体を少し剥がし、中の線を露出させますが、慎重に作業を進めることが重要です。
線が見えている部分が確認できたら、次にその部分をしっかりとつなぎ合わせます。
線を合わせて、接触部分をしっかりと固定します。
この際、セロハンテープを使うと非常に効果的です!テープでしっかりと巻きつけることで、線が再び切れるのを防ぐことができます。
ただし、セロテープで修理するには、銅線の被覆を剥いてつなぎ合わせる必要があります。
さらに、音が聞こえない原因が他にないか確認することも大切です。
たとえば、接触不良が原因で音が途切れることもあるため、つなぎ直した部分がしっかりと固定されているか確認します。
これで音が戻れば、修理成功です。
最後に、修理後はイヤホンをしばらく使ってみて、状態を確認しますが、音質が正常であれば、問題なく使用できるでしょう。
万が一、再度音が途切れる場合は、別の部分で断線が起きている可能性があるため、再度点検が必要です。
以上のように、イヤホンの線が切れたときでも、簡単な直し方を知っていれば、自分で修理が可能です。
これにより、急な出費を避け、愛用のイヤホンを長く使うことができるでしょう。
イヤホンの簡単な直し方
直し方
断線
危ない
知恵袋
ブツブツ
イヤホンの線が切れたら、簡単に直す方法があります。特に、断線している部分を見つけることが重要です。プツプツ音がする場合は、修理のサインです。知恵袋などの情報を活用し、急に聞こえない状態になった時の対策を学びましょう。セロハンテープで固定するだけで、再度使える状態に直せます。
- セロハンテープでの応急処置法
- プツプツと音が切れる時の対処法
- ハンダなしで修理する手順と知恵袋
- イヤホンの線を直す際の注意すべき点
- 有線イヤホンの断線防止に効果的な方法を解説!
- イヤホン線が切れた場合の対処法まとめ
セロハンテープでの応急処置法
イヤホンを使用していると、突然音が聞こえなくなることがあり、有線イヤホンの場合、線が切れたことが原因で、片方しか音が聞こえないという事態に直面することが多いです。
このような状況に遭遇した際、セロハンテープを使った応急処置法が非常に役立つので、セロハンテープを使った簡単な修理方法をご紹介します。
他の部分でも解説していますが、セロハンテープでの修理はあくまで応急処置です!しっかり確実に修理するならハンダ付けやイヤホンプラグの交換が必要です。
まず、イヤホンの線が切れた場合、その断線部分を特定することが重要です。
線のどの部分が切れたのか、または中の線が見えているのかを確認しますが、注意が必要なのは、切れた部分が露出している場合です。
露出している部分が片方だけなら、強度不足でもう片方も断線する可能性が高くなる為、早めの修理が必要です。
次に、見つけた断線部分を修理するための準備を行います。
セロハンテープを用意し、切れた線をしっかりと固定しますが、具体的には線を元の位置に戻し、セロハンテープで巻きつけることで、最低限の接触を保つことができます。
この修理方法は、ハンダなしで行えるため、特別な道具を必要としない点が魅力です。
この方法は、あくまで応急処置であるため、長期間の使用には向いていませんが、急に音が聞こえなくなったときには非常に効果的です。
セロハンテープで固定した部分がしっかりと接触していれば、音が戻ることが期待できます!もし音が戻らない場合は、他の部分に断線がある可能性も考えられるため、追加の点検が必要です。
また、セロハンテープを使った修理を行う際は、接触部分がしっかりと固定されていることを確認することが重要です。
これにより、プツプツと音が切れる現象を防ぐことができ、しっかりと固定された状態であれば、一時的にでもイヤホンを使うことができるでしょう。
応急処置を行った後は、イヤホンの使用状況を定期的に確認することが大切です。
音質が悪化したり、再び音が聞こえなくなったりした場合は、すぐに修理を検討する必要があります。
知恵袋などのオンラインリソースを活用することで、他のユーザーの経験を参考にしながら、より効果的な修理方法を見つけることもできるでしょう。
このように、セロハンテープを使った応急処置法は、イヤホンの線が切れた際の簡単な直し方の一つとして非常に有効です。
急に音が聞こえなくなったときに役立つこの方法を覚えておくと、いざというときに安心です。
プツプツと音が切れる時の対処法
イヤホンを使用していると、音がプツプツと切れる現象に悩まされることがあり、この問題は非常にストレスを感じさせるもので、特に音楽を楽しむ際には致命的です。
なぜこのようなことが起こるのか、そしてどのように対処すればよいのかを詳しく見ていきましょう。
まず、音がプツプツと切れる原因の一つは何度も解説している「断線」です。
イヤホンの線が内部で切れていると、音が途切れることがあり、この断線は、イヤホンを頻繁に巻きつけたり、引っ張ったりすることで発生しやすくなります。
具体的には、プラグ部分や接続部が弱点となり、ここが傷むと音が途切れがちになりますし、中の線が見えているような状態は、危ないサインです。
この場合、早急に修理が必要です。
次に、接触不良も音が切れる原因の一つと言え、イヤホンのジャック部分や接続部が汚れていたり、異物が挟まっていたりすると、正常な接触が妨げられます。
この場合、接続部分を清掃することで改善できることがあります。
特に、イヤホンを長期間使用していると、埃や汚れが溜まりやすいので、定期的なメンテナンスが大切です。
他に、用するデバイスの設定や状態も影響します。
例えば、スマートフォンやPCの音量設定が適切でない場合、音がプツプツと切れることがありますし、音質設定やBluetooth接続の状態も確認し、必要に応じて調整を行うことが重要です。
このような対策を行っても改善しない場合は、イヤホンそのものに問題があるかもしれません。
古いイヤホンや安価な製品では、内部の配線が劣化している可能性があり為、修理を検討するか、新しいイヤホンの購入を考える必要があります。
プツプツ音がするイヤホンの修理方法として、セロハンテープを使った一時的な応急処置も有効です。
線が切れている場合は、セロハンテープでしっかりと固定することで、音が戻ることが期待できます。
ただし、これはあくまで一時的な対策であり、根本的な修理が必要です。
このように、音がプツプツと切れる場合には、いくつかの原因が考えられますが、それぞれの原因に応じた対策を講じることで、快適な音楽体験を取り戻すことが可能です。
定期的にイヤホンの状態をチェックし、適切なメンテナンスを行うことが、長持ちさせる秘訣です。
ハンダなしで修理する手順と知恵袋
イヤホンの断線をハンダ付けなしで断線修理する簡単な直し方を解説します。
写真のように赤色のグリップは、本来、VVFケーブルの被覆をむいたりリングスリーブをかしめる時に使用する工具ですが、小径のリングスリーブならイヤホンの断線修理に使えないこともありません。

イヤホンの断線を修理するには、圧着端子という手もある事を解説しましたが、S.fields.incの圧着端子セットは、様々な端子がセットになっているので、サイズに合わせて圧着することが出来ます。
様々な種類の端子がセットになっているので、その場で合わせながら必要な端子を見極められるので、初心者におすすめです!
右側の青いグリップのものは、単に線のカットと被覆を剥く機能しかありませんが、電子工作用の信号線などの細い線にも対応しています。
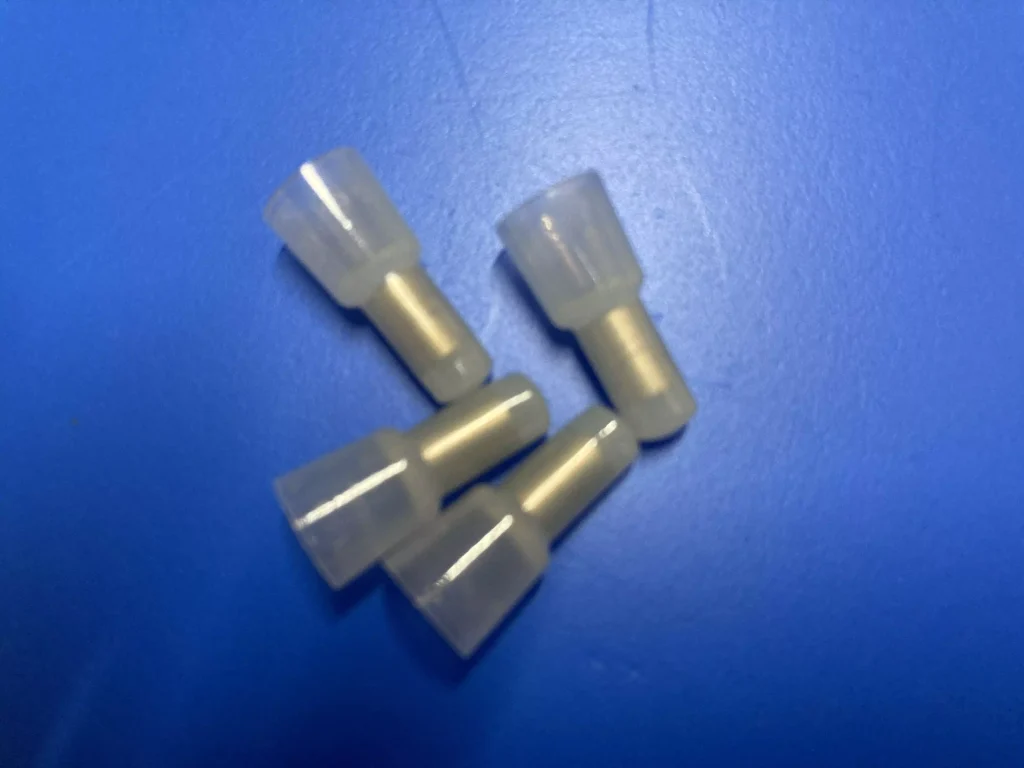
これが有線イヤホン断線の修理に使用した電気工事用のスリーブです。
写真だと伝わり辛いですが、なかなか大きいです。(その辺のホームセンターでどこでも手に入ります。一番小さいものを選びます)
ホームセンターでは単品で販売している事が一般的ですが、LIKENNYの裸圧着端子は、各種サイズがそろっているのでおすすめです。
配線をするのであれば、1セット持っていても良いでしょう。


カシメ工具は、カシメサイズにあった穴に取り付けて力いっぱい握ると線が圧着して簡単に接続されます。
最初に断線した線の被覆をスリーブの長さに剥いて、線同士をよっておくのがポイントです。
中途半端にかしめた状態だと途中で抜けてしまいますし、かしめた部分が邪魔で意外と使い辛いので簡単ですが、あくまで簡易的な方法と考えておきましょう。
ハンダを使用した断線イヤホンの簡単な直し方
断線イヤホンを修理するならハンダ付けをした上で、熱収縮チューブなどで断線部分をカバーする方法が一般的で簡単な直し方です。

ハンダこては最近どこの100均でも手に入るので、イヤホンの断線を修理する程度なら100均のハンダこてで十分です!
もし、一気に電子工作に必要なセットを揃えたいなら、SREMCHのはんだごてセットが評判がよくおすすめといわれています。
温度調整も可能なので、電子工作だけに関わらず、様々な用途に使用可能です。
半田付けのやり方についてはこちらの記事で詳しくまとめているので参考にしてください。
イヤホンジャックは通常の電気量販店では販売していないので、毎度おなじみの秋葉原や電子パーツを取り扱っている秋月電子やアマゾン・楽天などでも取り扱っている業者が沢山あります。
イヤホンジャックにはサイズがありますので、あらかじめどれくらいの径か調べた上で購入しましょう。

iPhoneのイヤホンプラグで使用されている一般的な、ステレオミニプラグアダプタはコレです!iPhoneのイヤホンプラグが切れてもこれで修理可能です。
画像の様に、この部品は矢印の部分にねじがきってあるので分解する事が出来ます。

画像のピントが少しずれていますが、分解すれば端子が三つある事が分かります。
一番の端子はアース線でコモン端子、二番と三番の端子は右と左のイヤホン端子で全部でみっつの端子があります。
半田付けをする前に一度カットした配線を繋げてみてちゃんと両耳で聞こえるか確認しましょう。
イヤホンの端子は殆どが中心の被覆に覆われている線が左・右のイヤホンの線で、中心を覆うようにばらけた線が共通線です。
断線修理した有線イヤホンが片耳しか聞こえない場合や、ブツブツ切れる時や、急に聞こえない時はハンダ付けが不十分で結線箇所がぐらついて居たり、ついて居ないのが原因です。
イヤホンの線を直す際の注意すべき点
イヤホンは私たちの日常生活に欠かせないアイテムですが、有線イヤホンの線が切れたり、断線したりすることはよくあります。
ここでは、イヤホンの線を直す際に注意すべき点について詳しく解説します。
他の章でも少し触れましたが、イヤホンの線が切れて、ブツブツと音が途切れる場合や、中の線がみえている場合でも、これと言って注意する点はありません。
あえていうと、作業中にカッターやハサミ、半田ごてを使って火傷やケガをしない事くらいでしょうか?
イヤホンの駆動に印加されている電圧は非常に低電圧の為、むき出しの配線に人が触っても、何も感じないでしょう。
電圧が低すぎて、濡れた手で触ったとしても感電はしないと思います。
ですが、電気配線は基本的に手袋を使用し、万が一の事故防止の為に、濡れた手で作業しない事は当然の基本と言えます。
次に、修理の際には適切な道具を準備することが大切です。
基本的には、セロハンテープやハサミがあれば簡単に修理を行うことができます。
ハンダなしで直す方法を選ぶ場合、セロハンテープは非常に便利で、切れた線をしっかりと固定することで、一時的な応急処置が可能になります。
ただし、この方法は長期的な修理には向いていませんので、あくまで一時的な対応として考えてください。
次に、修理する際の具体的な手順を見ていきましょう。
イヤホンの断線部分を見つけますが、線を引っ張りながら、どの部分が切れているのかを確認します。
切れた部分が見つかったら、周囲の絶縁体を丁寧に剥がし、中の線を露出させますが、線が切れていても、他の部分が正常であれば、簡単に直すことが可能です。
露出した線をしっかりとつなぎ合わせます。
この際、線が切れた部分をしっかりと合わせて、セロハンテープで固定します。
テープでしっかり巻きつけることで、接触を保ちつつ、音が戻る可能性がありますが、切れた線を被覆のままセロテープで固定しても意味がないので、しっかりと銅線を露出させましょう。
複数の線がある場合は、それぞれの線を正しく接続することが大切です!間違った接続を行うと、逆に音質が悪化することがありますので注意が必要です。
L/Rを間違えて配線した場合は、左耳から右耳の音が聞こえてきますw
また、修理後はイヤホンの状態を確認することが大切で、音質が正常であれば、問題なく使用できるでしょう。
しかし、もし音がプツプツと途切れるようであれば、再度確認する必要があり、他の部分で断線が起きている可能性も考えられるため、全体を点検することが重要です。
修理を行う際には、知恵袋などのオンラインリソースを活用することもおすすめです。
他のユーザーが実際に行った修理方法や注意点を参考にすることで、より効果的な修理が行えるでしょう。
同じような症状を経験した人のアドバイスは非常に役立ちます。
最後に、イヤホンの線を直す際には、使用後のケアも忘れずに行いましょう。
例えば、使用しない時はイヤホンを丁寧に巻いて保管することで、摩耗を防ぎ、次回の使用時に断線を避けることができます。
これにより、長期間にわたって快適にイヤホンを使用することができるでしょう。
このように、イヤホンの線を直す際には、いくつかの注意点があります!安全を確保し、適切な道具を使い、丁寧に作業を行うことで、問題を解決することが可能です。
有線イヤホンの断線防止に効果的な方法を解説!
有線イヤホンの断線防止には、以下の方法が効果的です。
使用中
- プラグの付け根を無理に引っ張ったり、曲げたりしない。
- ミニジャック部分を丁寧に扱い、擦れたり引っかかったりしないようにする。
- コードをきつく巻きつけたり、無理に引っ張ったりしない。
- コードクリップを使う
コードクリップを使うと、ケーブルをまとめることができ、移動中にコードが引っかかったり、擦れたりすることを防ぐことができます。
保管
- イヤホンを使わないときは、専用のケースに入れて持ち運ぶ。
- ケースに入れる前に、ケーブルを軽くまとめておく。
- ケースは硬めの素材のものを使う。
専用のケースに入れて持ち運ぶことで、イヤホンを外部からの衝撃や摩擦から守ることができます。
その他
- 断線しにくいイヤホンを選ぶ。
断線しにくいイヤホンには、以下のような特徴があります。
- コードが太い
- プラグやミニジャック部分が丈夫
- コードの分岐部分に保護キャップが付いている
おすすめの断線防止グッズ
- ケーブルプロテクター
- ケーブルを覆うことで、摩擦や衝撃から保護することができます。
- 様々な種類があるので、イヤホンのケーブルの太さに合ったものを選ぶことができます。
- イヤホンジャックカバー
イヤホンジャックに挿しておくことで、ホコリやゴミの侵入を防ぎ、断線を防ぐことができ、さまざまなデザインのものがあるので、イヤホンに合ったものを選ぶことができます。
これらの方法を参考に、イヤホンの断線防止を心がけてください。
イヤホン線が切れた場合の対処法まとめ
有線イヤホンは、音楽やポッドキャストを楽しむための便利なアイテムですが、使用頻度が高い分、イヤホンの線が切れることも多くあります。
イヤホンの線が切れた場合、聞こえない部分が出てきてしまい、音質が低下することが危ないです。
そこで、今回はイヤホンの断線を防ぐ方法や、線が切れた時の簡単な直し方についてまとめてみました。
まず、イヤホンの線が切れる原因としては、日常的な使用による摩耗や、無理な力がかかることが挙げられます。
イヤホンを頻繁に巻きつけたり、引っ張ったりすると、内部の線が断線するリスクが高まります。
これを防ぐためには、正しい取り扱いが重要です!イヤホンを使用しない時は、セロハンテープや専用のケーブルホルダーを使って、丁寧に保管することが推奨されます。
もし、イヤホンの線が切れた場合や中の線が見えてる時は、焦らずに修理を試みることができます。
特に、ハンダなしで簡単に直す方法がいくつかあります。
切れた部分を見つけたら、周囲の絶縁体を少し剥がし、中の線を確認し、中の線が見えてる場合は、プツプツとした音が聞こえることもありますが、ここで注意が必要です。
次に、見えている線をしっかりとつなぎ直し、テープで固定します。
セロハンテープを使うことで、簡単に補強が可能ですが、この時、線が切れる原因となる部分をしっかりと覆うことで、再度の断線を防ぐことができます。
テープで固定した後は、しばらく様子を見て、再び音が聞こえるか確認します。
知恵袋やインターネット上では、イヤホンの直し方に関する情報が豊富にあり、他のユーザーが実際に試した方法を参考にすることで、自分でも簡単に修理ができるかもしれません。
急に音が聞こえなくなった場合は、まずはケーブルの状態を確認し、適切な対策を講じることが大切です。
さらに、イヤホンの断線を防ぐためのアイデアとして、ケーブルプロテクターやスリーブを使用するのも効果的です。
これらのアイテムを使用することで、摩擦によるダメージを軽減し、長期間にわたって安心して使用することができます。
イヤホンの線が切れるのを防ぐための習慣を身に付けることも重要です!例えば、イヤホンを使った後は、必ず丁寧に巻いて収納することや、引っ張らないように心掛けることが、長持ちさせる秘訣です。
これにより、切れるリスクを減らし、快適な音楽ライフを楽しむことができます。
以上のように、イヤホンの線が切れてしまった場合でも、簡単な直し方や断線防止策を実践することで、長く愛用することが可能です。
正しい知識を持って、ぜひイヤホンを大切に扱ってください。
イヤホン線が切れて、断線修理するときの簡単な直し方やポイントをまとめます。
まず、感電して危ないという危険性からまとめると、イヤホンの動作電圧は数mV-1Vと非常に低電圧駆動のデバイスです。
その為、感電の心配はまずありませんが、パワーアンプ付きの家庭用のスピーカーから取れる有線イヤホンに関しては、漏電した場合この限りではありません。
この場合は、電圧計や検電器を使用して、漏電しているかどうか確認する必要があります。
AstroAIのテスターは、様々な端子や機能がデフォルトで付属している為、非常にお勧めです。
また、Bluetoothの無線イヤホンに関しては、電子回路制御で故障個所を特定するのが非常に困難ですので、個人で簡単に断線修理するのはほぼ不可能と言っていいでしょう。
Bluetoothの無線イヤホンは感電の危険性こそありませんが、内部にリチウムイオン電池を使用しています。
もし、過充電や過放電またはぶつけてヒビが入ったりした場合は、内部のリチウムが反応して発熱や煙がでる危険がありますが、容量の低さから火災まで発展する事はほぼないでしょう。
続いて、有線イヤホンが断線した時の対応方法ですが、線の途中で断線しているならばハンダ付けしない修理方法とハンダ付けで修理する方法の2通りの簡単な直し方があります。
ハンダなしで修理する場合は、スリーブを使用して工具で圧着しますが修理した部分にコブが出来てカバンや服などに引っかかって使いにくいというデメリットがあります。
簡単な直し方ではありますが、あまりお勧めは出来ません!しかし、ハンダ付けで修理する場合はあらゆる断線に対応できます。
特に、イヤホンジャックの根元の断線は、イヤホンジャックパーツを購入して半田付けするしかないので、ハンダ付けの修理でしか対応できません。
最後に、高価な有線イヤホンなら買い替えるより断線を自分で修理した方がコスパ最高と言えます。
筆者の回りの人は殆どがアイホンiPhoneですので、公式修理のサポート窓口URLを載せておきます。
参考


















コメント